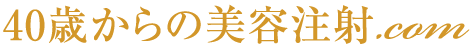公開日: |更新日:
ビタミン注射・ビタミン点滴の痛みはどのくらい?
内科や美容皮膚科で受けられるビタミン注射・ビタミン点滴。施術時間が短く、手ごろな価格帯で提供されていることから多くの女性に選ばれていますが、果たして痛みはあるのでしょうか? ここでは、ビタミン注射・点滴の痛みについて詳しく解説。痛みが起きた際の対処法についてもまとめています。
ビタミン注射・ビタミン点滴の痛み
病院で受ける注射と同じ程度
ビタミン注射やビタミン点滴で使う針は、予防接種や採血の際に使われる注射針と同様の針が使われます。針の太さもほぼ同じなため、刺したときに多少チクっとした痛みを感じるでしょう。また、ビタミン注射の場合、静脈注射と筋肉注射の2種類があります。
即効性を感じたい方は静脈注射、持続性を高めたい方は筋肉注射がおすすめ。ビタミン注射は、点滴に比べてじわじわと効果があらわれる持続性のある方法です。
静脈注射
ビタミン注射・ビタミン点滴で多くのクリニックが行っているのが静脈注射です。予防接種のときのような痛みで、刺すときにチクっとした痛みがありますが我慢できるほどでしょう。ただし、ビタミンCを注射する際は、ビタミンCの分子が大きいために静脈注射をしたときに血管に痛みが起きることがあります。
筋肉注射
筋肉の組織の間に入れ込むので、注入中は痛みがあり、注入後も筋肉痛のような感覚がありますが我慢できる程度です。筋肉注射は上腕か、お尻の筋肉の部分に注射します。腕よりもお尻に注射したほうが痛くないという方が多いので、痛みに弱い方はお尻への注射が可能か尋ねてみましょう。
筋肉注射のほうが痛い
ビタミン注射は、静脈に入れるよりも筋肉注射のほうが痛みの度合いが強いとされています。クリニックによって治療の方針は異なりますが、ビタミン注射は静脈注射のみで対応しているというところが多いでしょう。注射の場合はすぐに済むため、がまんできる痛みですが、痛みに弱い方は静脈注射のほうがおすすめです。
なお、ビタミン点滴の場合はすべて静脈注射です。ゆっくり休みながら投与できるので、リラックスしながら受けたいという方は点滴がおすすめ。時間をかけたくない方は注射が適しています。どちらもビタミンの効果に変わりはないので、自分の好きなほうを選んでください。
血管に痛みが起きることも
ビタミンCを注射や点滴で取り入れる場合、注入の間、軽い血管痛が起こることがあります。また、ビタミンCの浸透圧によって血管に負担がかかって痛みを起こすこともあるでしょう。とくに高濃度ビタミンC点滴の際によくみられる現象です。血管痛が起きた場合は、点滴の速度を落としたり点滴をあたためたりして対処します。点滴に緩衝材を注入することでも痛みを軽減できるので、がまんせずに施術者へ伝えましょう。
また、血管痛や違和感が出た場合、血管の外に薬剤がもれている可能性も考えられます。どうしても痛みが強い場合には必ず施術者に診てもらってください。一度針を抜いて刺し直すなどの対処が必要です。
痛みに寄り添ってくれるクリニックを選ぶ
痛みに弱い方や注射が苦手な方がビタミン注射やビタミン点滴を受けたい場合、しっかりと不安を受け止めて対応してくれるクリニックでなければ、施術中もいやな気持ちになってしまうかもしれません。注射への恐怖から、その場で体調を悪くしてしまう可能性もあります。はじめのカウンセリング時には、注射が苦手なことをきちんと伝えましょう。
クリニックによっては、極力痛みを感じないようにベテランの医師が対応したり、注射針を細くしたりと工夫してくれるところもあります。痛くないように対応してくれる親身なクリニックなら、安心して任せられそうです。